★2008年1月18日(金)~20日(日)「旧・東海道、静岡駅~磐田駅」




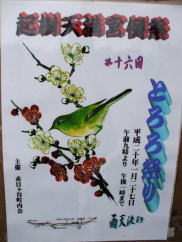













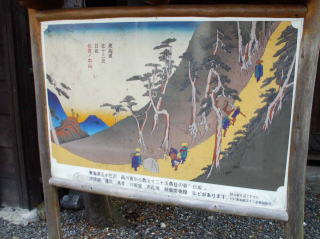







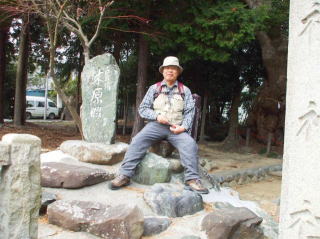


◆ど真ん中の宿場は27次・袋井宿、いろいろ工夫しています。
「どまん中 袋井宿は 町おこし」
◆磐田市(見付宿)で今回は終了
「富士山を 見つけて名にす 見付宿」
このページのトップに戻る
前のページへ 次のページへ
.
.
.
.