








★2010年6月11日(金) 〜14日(月)「中山道、本山宿(日出塩)〜贄川宿〜奈良井宿〜鳥居峠〜薮原宿〜薮原宿〜宮ノ越宿〜福島宿〜上松宿」

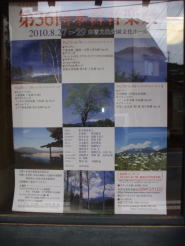







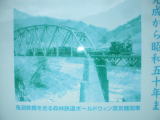






















<6月11日(金)移動日=新宿〜塩尻>
新宿駅午後3時発のあずさ号に乗車したのは、清水・西・村谷の3名。
塩尻駅までの2時間半、まだ空いている車中を往復する売り子さんから追加の飲み物を仕入れて、明日から3日間の行程について協議した。
週明けにかけて天気が崩れていくという予報なので、日程を前倒しで消化することとし、初日のうちに鳥居峠を越えてしまうことで一致した。
5時半過ぎ、塩尻駅そばのビジネスホテル よこやまに3度目の投宿。
夕食が付いていないので、荷物を置いて直ぐに先月と同じ養老の滝系統の居酒屋に出向く。
週末の夕刻とあってまずまずの入りで、我らは玄関近くの小上がりに席を確保した。先月、5時開店とともに入った際に、てきぱきと注文をとってくれた長い睫毛のS嬢(勤続2年)は2階の大宴会の担当だったが、挨拶に降りてきた。
本日の担当は、入店6ヶ月・19歳の初々しいS2嬢で、偶々S嬢と同じく、これから我らが目指す木曽路方面から通勤しているとは奇遇、奇遇。
素直にお勧めに従って、ヘルシーなツマミをあれこれと注文し、生ビール→焼酎ボトルとお定まりのコースになり、前途の健闘を誓い合って宿に戻った。
明日に備えて二次会を軽く切り上げ、早々に就寝した・
<6月12日(土)本山宿(日出塩)〜贄川宿〜木曽平沢〜奈良井宿〜鳥居峠〜薮原宿。歩行距離は約19キロ>
快晴・真夏日の朝、相変わらず種類が多いおかずで朝飯をたっぷりと平らげ、塩尻駅へ向かう。今回は3人とも半ズボン姿で統一している。
中央西線で中津川方面に乗車し、二つ目の日出塩駅を目指す。車窓から見えたブドウ畑の前回は何もなかった棚に、青い木々が伸びていた。
車中には、週末を利用して木曽路を散歩するらしいハイカーが何組も乗り合わせていたが、まだ木曽路に入らずに下車した我らを不思議そうに見送ってくれた。
8時半前、日出塩公民館横から3日間の旅?にスタートする。5キロ先の贄川宿までは、国道19号線と奈良井川(下流は信濃川)に沿って歩くことになる。
程なく「是より南木曽路碑」が出現する。奈良井川に注ぐ澄み切った清流・境川が、江戸時代には文字通り尾張と信濃の境界だったそうで、尾張藩の領地の広さに驚かされた。
暫くは国道と並行する山沿いの旧道に入るので、暑さが凌げてありがたい。馬頭観音像が2箇所もあり、往時の難所振りが偲ばれた。
国道との合流点・桜沢集落付近は村人が自力で岩を削って開削したため、わが国初の有料道路だったというが、いささか信じがたい。
国道脇には、明治天皇の休息所だった茶屋本陣跡の大きな家が残っていた。
若御子一里塚跡からまた旧道で、車が少なくて好都合。休日歩きの我らは、平日よりマシとはいうものの、大型車とすれ違いで神経を使わずに済む。
また国道と合流し、左手に贄川駅、宿場の入り口だ。
線路を跨ぐメロディー橋の上に、金管が整然と並んでいて、傍らの木槌で順番に打っていくと木曽節が聞こえる仕掛けになっている。
橋を渡った左手が贄川関所跡。中の木曽考古学館には入らず、木のベンチで一息入れる。
村谷は早くも2本目のペットボトルを飲み干した。
ここからの旧道沿いに町並みが、木曽11宿最初の贄川宿。名の由来は、河原で熱い湯が湧き出していたためだそうだが、今は温泉がない。中山道沿いには温泉が少なく、諏訪湖が突出している。
昭和5年の大火で古い家並みが殆ど失われたが、わずかに残る国の重文・深澤家住宅が往時の風情を継承している。
宿場はずれの国道との合流点・桃岡に江戸から63番目の押込の一里塚跡がある。
続く長瀬集落の先にある道の駅「くらし工芸館・木曽ならかわ」でトイレ休憩。
漆器や新鮮野菜など豊富だが、我らは購入する余裕がない。
この付近の地名「楢川」は、古い宿場町の奈良井と贄川を足して作ったという。
日差しがどんどん強くなってきたので、楢川支所先の木曽くらし漆器館の木陰に入る。「送られつ をくりつ はては 木曽の秋」という芭蕉句碑がある。同じ碑が馬籠宿を出た新茶屋にもあるそうで、7月が楽しみだ。
心地よい旧道を進むと家並みが見えてきて、木曽平沢駅。先週の土曜・日曜には奈良井宿と共催で漆器祭りがあり大変な人出だったそうだが、打って変わって本日は静かな佇まいが続く。見事な日本家屋の整列は国の重要伝統的建造物保存地区だ。
町外れからの旧道は国道沿いになっていたが、我らは中部自然歩道を選択して、川沿いの堤防を行く。左手には見事な木造校舎の楢川小学校。
奈良井大橋を渡り、丁度着いた循環バスに乗る楢川中学校の女子生徒を見送って、木造の奈良井駅に着く。
土曜日を利用した散策する人々が次々に現れ、一遍に都会の喧騒?に似てしまう。
電柱が完全に地中に埋設され、建物が見事に古風に統一された町並みは、平沢同様に国の保存地区だ。3人とも当地は再訪だったが、改めて感心した。
先ずは、今夜の宿・かとう民宿へ。ウオシュレット完備の最新設備が売り物だ。荷物は置いて、水だけ持って出立、まずは昼飯。
筋向いの越後屋に入店し、ザル蕎麦2枚+五平餅2個=1,500円のセットを注文すると12時ジャストに出てきた。鳥居峠越えが控えているのでアルコールは夜までお預け。味は観光地の標準クラスと判定した。次々に客が入ってきて、出る頃には満席だった。目の前に杉の森酒造があることを確認して夜の再訪を楽しみに歩き出す。
緩やかな上り坂を上って行き、町外れの鬼門に当たる鎮神社に参拝、峠越えの無事を祈願する。ここからの山道が、いよいよ鳥居峠。かっての難所も、明治以降に石畳が整備されたり、急斜面を回避したため、今は当時の険しさがあまり残っていない。昔あった下の茶屋と中の茶屋は、跡が残るだけ。かって峠の茶屋と呼ばれた跡に建つ立派な休憩施設で一息入れていると、我らが目指す薮原駅方面から来た単独の男性と一緒になる。
広い林道は回避し、教えてもらった山道を上っていくと、標高1,197mの「村界」標識があり、この地点が頂上らしい。
その先は旧道が途絶えているため、明治期に開かれた林道に下りる。御嶽遥拝所から木曽御嶽山の全容がくっきりと見えた。
義仲硯水と「ひばりより 上にやすろう 峠かな」の芭蕉句碑がある丸山公園は立ち寄らず、一目散に下山する。JR線が見えてきて薮原宿。
かってはお六櫛というブランド品があったそうだが、今は静かな田舎町。
薮原駅に着くと、JRハイキングご一行様が、中津川方面に帰っていった。
戻りの電車までは1時間あるので、駅で効いた国道沿いのドライブイン 一休で、生ビールと自家製漬物で休憩。
電車で奈良井駅へ戻り、日本最大幅の総ヒノキの木橋・木曽の大橋を見学し、杉の森酒造で、吟醸酒と原酒を各1本購入して かとう民宿へ帰還する。
盛り沢山の夕食を、女性二人連れ・男性二人連れ・幼児+若夫婦と10名全員で賑やかに食卓を囲む。またもビールで何とか平らげて、部屋に戻る。心地よい疲れが酔いを早めたため、原酒1本は明日に残して就寝した。
<6月13日(日)薮原宿〜宮ノ越宿〜福島宿>
本日の朝食も、賑やかに9名が勢ぞろいして、1階の座敷で楽しく済ませた。
我らは7時半過ぎに、民宿かとうを一番先に出発、昨日見残した寺社を参拝する。
先ずは最寄の大宝寺へ。早朝から法事がある模様で、慌しく檀家の人たちが行き来しているので、マリア地蔵の参拝は諦めて長泉寺へ移動する。お茶壷道中の定宿に相応しい、後ろの山稜に負けない堂々たる建物だった。
ペットボトルに清水を詰めて奈良井駅に向かう。
電車で鳥居峠を軽々と越えて薮原駅に下車。駅前広場では、老人集団が清掃中。
朝の挨拶をしながら小川まで来ると早起きの老婆?に確認して、橋の下から一里塚への近道を目指す。
木曽村民センターの広場で、D51のSLと薮原一里塚を一緒に撮影して先へ進む。
地下のガードで鉄道を潜って、国道に合流。皇女和宮の7万人もの行列が延々と3日間も続くのが対岸からみえたという吉田洞門、山吹トンネルを通過。
巴潟への分岐で国道と分かれる。
「山吹も 巴もいでて 田植かな」という芭蕉の弟子・許六の碑がある。木曽谷では米の生産量が少なかったそうだが、権兵衛峠経由で伊那の米を持ち込み芳醇な酒の生産が行われていたという。今でも田圃が少ないが、酒は水次第と3人の見解は一致した。
木曽川の幅が狭い巴潟の深みで、かって巴御前が水浴したと伝えられる。
今や田んぼが多い徳音寺集落に、黒一色で統一した近代的な建築物があった。
木曽義仲・巴御前・義仲の母小枝御前の墓が仲良く立ち並ぶ徳音寺に参拝する。
この地から京の都まで上洛したエネルギーがあったとは想像できないほど、ゆったりとしたさとの風情だ。
続いて、竹下内閣のふるさと創生資金を活用して作られた義仲館に入る。熱心なボランティアの説明と、懇切なパンフレットで、300円の入場料が高くない。平成の始めから10年頃まで6回だけ行われたらしいミス巴御前の写真が飾られていたが、
いずれもふくよかな平安美人だった。
義仲をこよなく愛した松尾芭蕉が、近江の義仲寺に埋葬されていたのを、吉田・滝澤・清水の諸兄との東海道歩きで通過したことを思い出した。
宮ノ越宿はこれといった特徴がなく、むしろ奈良井宿の町おこしの成功振りが珍しいと感じた次第。
宿はずれに69番目の宮ノ越一里塚がある。
緩やかな上り坂の右手に、巨大な敷地の生コン工場が広がる。
鉄道を越えると右手に、無人の原野駅。
昼食に適当な時間が近づいてきたので、地図を持ち寄って協議する。清水が、木曽観光連盟作成の「信州木曽路・中山道を歩く」パンフレットで道の駅を発見したのでそこに決定。
67里38町の中山道中間地点の碑の先から、国道に左折する。まだ半分しか歩いていない。
「道の駅日義木曽駒高原」ほお葉祭り会場の一つになっていて、木曽の名産物が即売されていた。我らは食堂に直行し、しっかりと丼飯で腹ごしらえする。
足取りも軽く旧道に戻る。上田集落の出尻一里塚は所在が不明だった。
木曽義仲と巴御前に学問を習わせるため京都の北野天満宮から勧請したという手習天神は、意外にに小ぶりだった。
木曽福島宿の入り口を象徴する冠木門を通過、左手の高台にある福島関所跡に立ち寄る。
中山道は特に入り鉄砲より出女に厳しかったと伝えられるが、東海道より山坂は多いが女性にとって往来しやすい環境があったためと勝手に推測した。
街道に下りると本日が最終日のほお葉祭りの掲示が続くので、道なりに広小路の本会場に向かう。思ったより狭い会場には、客より売り子の姿が目立つ。先ずは焼き鳥と生ビール。旨い。
本日の宿を聞かれて、さらしなや と伝えると、会場でほお葉つくりを指導していた旅館の女将が挨拶に現れ、そんな次第で本日の夕食が作れないと話してくれた。
2時過ぎに旅館に入って寛いでいると、会場から女将がお茶請けとしてほお葉巻を届けてくれた。
4時半から順番に入浴し、夕食に出かける。
木曽川が度々氾濫したので、かっての宿場が高台にあるのが特徴だ。駅前の蕎麦屋でビールと山菜・冷や奴で軽く腹ごしらえ。帰途にあったサティで追加の木曽の中乗りさん4合びん1本とバライティに富んだツマミを調達して帰館する。
明日は半日コースなので、昨日から持ち越しの杉の森原酒と合わせて痛飲し、ぐっすりと寝入った。
<6月14日(月)中山道・福島宿〜上松宿>
昨夜、木曽福島駅前から帰館途中の午後6時ごろ、早くも雨がパラついてきたので、明日が驟雨ならばそのまま帰京することとして、残った酒を空けてしまい熟睡した。
関東甲信越地方が入梅した翌日午前5時、まだ雨が降り止まない。
しかし、広々とした立派な座敷で、料理自慢ながら昨夜はほお葉祭りで腕がふるえなかった女将の心尽くしの朝食を平らげているうちに、雨がすっかりと上がってしまったので、次の上松宿まで行くことにした。
午前8時、宿を後にして、昨日夕食を済ませた木曽福島駅に戻る。月曜日の朝とあって人影がない。
御嶽神社横から合併した木曽福島庁舎前を通過する。厳しい財政事情?を反映してプレハブ造りの簡素な建物だった。
程なく現れた塩淵一里塚は江戸へ70里・京へ67里と半分を踏破した実感が味わえるのが嬉しい。
国道とは微妙な距離を持った旧道に沿って、畑道を行く。
薄暗いトンネルも3人でわいわいと通過。
御嶽山に通じる元橋交差点から直ぐに旧道になる。
旧中山道からは意外に見えない木曽の御嶽山の遥拝所があったが、今は木々で遮られている。
この分では昼までは雨がなさそうな天気になってきたので、国道とJR線を見下ろす旧道をどんどん進む。
国道との合流地点が沓掛の一里塚跡。
左右の車に注意して行動を横断し、木曽川の橋の上から、錦帯橋・猿橋とならぶ日本三大奇橋のひとつ・木曽の桟(かけはし)を間近で鑑賞する。
芭蕉が「かけはしや 命をからむ つたかずら」と詠った当時の険しさは到底実感できないが、木曽川の急流と併せて往時を偲んでみた。
旧中山道は、どちらかといえば国道に近いが、歩道がないため「是より木曽路」に従ってそのまま対岸を歩くことにしたのが、ハプニングとの遭遇だった。
人気のない川べりの温泉旅館をのぞいて、遊歩道を利用してショートカット、車道に出て、程なく木曽の桟に着く。
全容を撮影するには、立派な木の階段を降りるのがよいが、何故か黄色いテープで封鎖されており「最近、熊が出ている」とのこと。
遵法精神豊かな我らは橋上からの撮影に留め橋をわたったが、先行した村谷がふとがけ下を見下ろすと、黒い影。小熊がいた。
慌ててシャッターを切り、車の往来が激しい道路を先行した。(上松駅の観光案内所によれば、山から下りた小熊が帰れなくなって川の両岸を行き来してるとのことでした)肝を潰して先を急ぐ。
赤沢自然休養村に続く森林鉄道跡から上松宿へ。
11時過ぎの電車で塩尻駅〜新宿に帰京する車窓から、激しい雨が見て取れた。
次回は、7月中旬に、上松宿から、寝覚の床〜妻籠宿〜馬籠宿〜中津川宿まで歩く予定です。
このページのトップに戻る
前のページへ 次のページへ
,
,
,